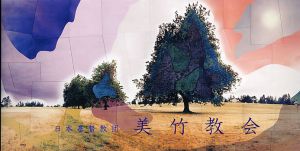「聖められた者として」詩編41:8~14、ヨハネ13:12~20
2025年4月6日(レントⅤ・左近深恵子)
親しい人が亡くなると、その人の死の間際のことが強い印象を私たちにあたえます。その人のことを思う度に死の前のことが思い返されます。まして相手から、このことを覚えていて欲しいと言われたり、このことをして欲しいと言われたことは心に残り、託されたことについて考え続けるのではないでしょうか。主イエスも弟子たちの心に残り続け、託されたことを担ってゆくようになることを願って、十字架にお架かりになる前の晩に、死を前にしたこの時だからこそ、彼らに語り掛けられたことでしょう。
それまでも主イエスは人々に対して語ってこられました。ガリラヤでも、エルサレムでも、サマリアでも、人々に福音を語り、その恵みを示すしるしを為さってきました。12章になると、最後の過越しの祭りを祝うために主イエスの一行がエルサレムに入られ、人々に語られ、それから立ち去って人々から身を隠されたことが述べられます。そして13章からは、弟子たちに集中して語っておられます。13章の冒頭には、主イエスが「この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれた」とあります。ご自分の時が来たと、ご自分が十字架で死なれ、その後復活され、父なる神のもとへと挙げられる時がいよいよ来たと悟られたので、ご自分が天へと挙げられた後、残される弟子たちを、ますます愛し、最後まで愛し抜かれました。主イエスが弟子たちに注いでくださる徹底的な愛を語ったその直ぐ後で、福音書は、その時既にユダの心に、悪魔が主イエスを裏切る思いを入れていたことを述べます。ペトロもこの後、主を知らないと主との関係を否定することになります。他の弟子たちも、逮捕された主から離れてゆくことになります。主イエスの愛とあまりにも対照的な弟子たちの現実です。主が弟子たちを愛されるのは、弟子たちが愛を受けるに相応しい者たちだからではありません。愛を受けたらそれ相応のものを主イエスに返すことが期待できる者たちだからでもありません。主イエスが見つめておられる者たちは、父なる神がご自分に与えてくださった一人一人です。愛の源はただ主なる神の側にある、その愛で愛し抜かれることを主はとりわけこの晩に彼らに伝えてくださいました。
その愛を主は先ず行いによって示してくださいました。夕食の席から立ちあがり、上着を脱いで、手ぬぐいを取って腰に巻き、たらいに水を汲んで、弟子たち一人一人の足を順に、洗っては腰に巻いた手拭で拭いてゆかれました。それは弟子たちにとって呆気にとられるような出来事でした。
乾燥したパレスティナの気候の中、サンダルのような履き物で一日砂埃舞う屋外を歩き回れば、足は砂埃にまみれます。家に入る前に足を洗うことが、人々の日常でした。自分の家に帰ったなら自分で洗うか、家の僕が洗ったようです。家に客人を迎えた時には、その相手に対する第一のもてなしとして、足を洗うための水を主人は用意させました。汚れた足を洗うこと、そのための水を用意することは、身分の低い者、特に奴隷がその役割を負っていました。先生であり主である主イエスが弟子である自分たちの足を洗うのは、関係が逆転してしまっています。ペトロが抵抗すると主イエスは、「私のしていることは、今あなたには分からないが、後で、分かるようになる」と言われます。また「もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる」と言われました。
この日主イエスはがなさった洗足はしるしでした。主イエスはよく福音を語るのに譬えを用いられますが、今日の場面では行いを用いて福音を示されました。上着を脱いで腰に手拭を巻き、奴隷のような出で立ちで自らたらいに水を汲んで、弟子たちの傍に近付いては身を屈め、その汚れた足をご自分の手で持ち上げて洗い、埃も土も何もついていない清潔な足を取り戻してくださる、この行為によって示したことは「後で、分かるようになる」と言われた主ですが、席に戻られると、「私があなたがたにしたことが分かるか」と言われます。後にならなければ分からないだろうが、それでも今、私がしたことを考えてみなさいと促されます。
主が彼らの足ではなく手などを洗われたのだったら、弟子たちはそこまで驚かなかったでしょう。関係が逆転しているとは言え、強く抵抗するほどのことではなかったでしょう。主が洗われたのは手や腕や顔ではなく、体の最も低い部分、地面の汚れに最も晒されてきて、その汚れを大いに纏っている足でした。その足と地面にご自分の顔を近づけるようにして屈んで洗ってくださった、その行いが分かるか、と問われます。自分がこの場に居たなら、「主は、高ぶらず、へりくだって人に仕えることを教えておられるのだ」、そう受け止めるくらいがせいぜいだろうと思います。しかし主は、ご自分の死によってもたらされることを示されました。十字架の死と、その死によって罪に塗れた彼らが清められ、罪から解放されることを示されました。十字架も、復活もまだ起きておらず、聖霊の導きを受けていない弟子たちには、このことが分かりません。それらのことが起きた時に、主が命をささげられたことで、この自分の罪も赦されているのだと分かるように、こうして十字架の意味を示すみ業を為さり、その意味を語られたのでした。
弟子たちはそれまで主イエスと自分との関わりを、主イエスとの接点の多さ、長さといったものによって捉えてきたのではないでしょうか。ガリラヤ湖で漁をしていた時、あるいは税を集めていた時、主が「私に従いなさい」と声を掛けてくださった驚きの出会いがあった、主の教えを沢山聴き、主のお働きを支えるために多くのことをしてきた、今日まで毎日のようにご一緒に歩き、一緒に食事をしてきた。その時間の長さ、交わした言葉の多さ、主のために自分がしてきた働きの量が、主との関わりを基礎づけ、強いものとしていると思っていたことでしょう。けれど主イエスは、主が洗うことによって、主と一人一人は関係づけられるのだと言われます。主によって洗われることで、主につながるのだと。この食卓を囲んでいる弟子たちは、主によって足を洗われた者たちの群れです。主によって洗われたことが、互いの接点です。更に十字架の後の弟子たち、そして私たちキリスト者は、十字架と言う同じ御業によってそれぞれ罪を清められた者であります。どこにいる者であっても、主によって洗われた者として、主の食卓を囲む者たちです。神のみ子が世に降られなければ、ご自分の命によって罪を贖ってくださらなければ、互いに結びつくことの無い者たち、互いに結びつき得ることを知らない者たちが、キリストによって、キリストの教会とされているのです。
弟子たちの足を洗い終えた主イエスは再び上着を纏い、席に戻られると、彼らの先生であり主であるご自分が弟子であり僕である彼らの足を洗ったのは、ご自分を模範にして、ご自分が為さった通りに行うためだと、互いに足を洗い合うべきだと言われます。主イエスと弟子たちの繋がりは、遣わす方と遣わされる者たちとも表現されています。福音を世に宣べ伝えるという同じ務めを委ねられ、同じ主から遣わされる者同士、互いに足を洗い合うべきであると言われます。“足を洗い合った方が良い”と勧めておられるのではなく、「洗い合うべきである」と断言されています。主の弟子であり、主の僕であり、主から遣わされる者である私たちは、主から教えられたことを、ただ知識として誰かに伝えて終わりません。十字架の福音は、私たちの命そのものに関わるものです。その福音を伝える私たちの日々に関わるもの、私たちの生き方そのものに関わるものです。主の十字架によって洗い清められているのだと知ることができたなら、その受けた恵みを覚えながら一歩一歩歩んで行こうと思います。受けた恵みを他者と分かち合いたいと思います。人からどう見られるかばかり気になり、どう見られるかが行動の根拠になりがちな私たちです。何かをするならそれに見合うものを求めてしまうのが当たり前の私たちです。「このことが分かり、その通りに実行するなら、幸いである」と言われます。山上の説教の「幸いである」と繰り返された教えを思い起こす語り口です。「このことが分かり、その通りに実行するなら」、主がそう言われたのは、その通りに実行できない人間の現実をご存知だからではないでしょうか。山上の説教で「幸いである」と告げながら、私たち自身では幸いと思えないようなことを次々と語られたように、互いに足を洗い合うことも、私たちにとって自明のことではありません。他者の足を洗うような隣人との関わりを自発的に皆が求めているなら、そして皆がその願いを実行に移してきたなら、教会の歴史も世界の歴史も違った道を辿ったのではないでしょうか。
見返りが見込めないもののために何かを差し出して損をすることを人との関係でも恐れてしまう私たちです。しかし、私たちが払わなければならない罪の値を払うために、キリストは命を差し出してくださいました。そうして救われた私たちだから、私たちの内側にあるのは、キリストからいただいた恵みです。足を洗い合うということは、注ぎ出しても、注ぎ出しても、溢れ出す十字架の恵みを、誰かと分かち合うことと言えるでしょう。キリストと関りの無いところで、高慢にならないように、へりくだっていなければと、自分の熱意と努力で思いと行為を注ぎ出そうとするなら、私たちは直ぐに枯渇してしまいます。礼拝においてみ言葉を受け、聖餐において糧をいただき、信仰について学び続け、そうして主から恵みをいただいた者として押し出されるなら、私たちの内側は空っぽのはずがないのです。
13章をもう少し読み進めますと、主は34節で弟子たちに新しい戒めをこのように与えておられます。「互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなたがたが私の弟子であることを、皆が知るであろう」。今日の箇所と同じような語り口です。「足を洗い合いなさい」を、「愛し合いなさい」に言い換えておられるとも言えます。愛するとはどういうことなのか、足を洗って示してくださった主が、愛し合いなさいと、そうすることであなたがたが私の弟子であることを皆に示すことができるのだと、言われます。弟子の群れ、つまり教会は、主イエスに足を洗っていただいた者たちの群れです。キリストに従う者同士の関わりは、自分の清さ、美しさを、背伸びをして競い合うようなものではなく、主イエスに倣って、汚れた足と地面に顔を近づけるようにして腰を屈めて互いの足を洗い合うような関わりです。礼拝において、神がその独り子を世にお遣わしになるほどに世を愛され、その独り子が私の足も洗ってくださり、永遠の命を生きるようにしてくださった、その事実に立ち直しては、足を洗い合い、祈り合い、支え合って福音を宣べ伝え、主の恵みを分かち合っていこうとする関わりです。
主イエスに足を洗っていただき、直接「互いに足を洗い合うべきである」と言われながら、主を裏切り、主を見捨てる弟子たちのこの先を見つめながら、彼らの足を洗い、彼らに語り掛けられた主の苦しみを思います。「あなたがた皆について言っているのではない」と言われる主の言葉は、何よりもユダを指しているのでしょう。主イエスは「私は、自分が選んだ者を知っている」とも言われます。何が人の心の中にあるのかよく知っておられる主イエスは、ユダや弟子たちの心の中にあるものを見通しておられながら、彼らを弟子として選ばれ、その一人一人のためにも十字架に至る道を歩んでこられました。「私のパンを食べている者が、私を足蹴にした」という聖書の言葉が実現するためであると言われます。これは先ほど共にお聞きしました詩編41:10の言葉であります。同じ食卓で共に食事をしてきた者、パンをいただき自分の糧としてきた者の中から裏切る者が出ることを語っています。主イエスと数えきれないほど食卓を囲み、祝福の祈りを捧げて分け与える主の手からパンをいただいてきた弟子たちの中から主を裏切る者が出ることも、神さまのご計画の内にあることを告げておられます。
ユダが闇に呑み込まれて主を裏切り、十字架の出来事が起こり、他の弟子たちも主を見捨てる時、主イエスとは、「私はある」と言われる方であると彼らが信じるようになるために、彼らが闇に覆われる前に言っておくと言われます。この福音書に多く登場する「私はある」というフレーズは、主が、ご自身が神であることを示される時に用いられる、定まった言い方です。自分たちの仲間の一人が主イエスを売り渡していたことを知る時、主イエスが逮捕され、有罪とされ、十字架で処刑される時、主イエスがどのような方であるのか、弟子たちが大きく深く揺さぶられる時、主は「ある」と言われる方なのだと思い起こすことができるように、先立って語られます。主イエスは神であるのだと、神であられる方が、自分たちと共にいてくださり、今も、この先もいてくださるのだと信じ、主を受け入れ、主が示された救いを受け入れるようになることを、彼らの闇を見つめながら、主は願ってくださったのです。
弟子たちは、主に従う道を貫けずに、主を裏切り、見捨てました。私たちは主に従うことを願いながら、自分の従う力の弱さ、足取りの不確かさによって自分の願いに自分で背き、結果、「互いに足を洗い合いなさい」と命じられた主を裏切ってしまう者です。自力で従っているのではなく、主によって遣わされているのだから、意欲も、力も、根拠も、理由も、源は主にあります。私たちの足を洗い合う生き方が不完全であっても、主が助けてくださり、欠けを補ってくださり、そうしてどなたが私たちの主であるのか、どなたが私たちを遣わしておられるのか、証する者としてくださるでしょう。「よくよく言っておく」と、これは大切なことなのだと念を押してから、み子が遣わす者を受け入れる人は、み子を受け入れ、更にみ子をお遣わしになった父なる神を受け入れるのだと言われました。主の恵を分かち合うことにもがき、足掻く私たちの営みを、主を指し示すものとして用いてくださるとの確信を与えてくださっていることが、私たちの力です。私たちの弱さや背きを十字架によって洗い清められたのだと信じ告白し、キリストの恵みを新たに思い起こし、聖餐の糧によって養われて、また互いに足を洗い合い、主を指し示すことへと踏み出します。