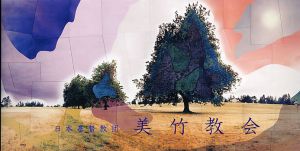「突き刺さる言葉」ゼカリヤ13:7、マタイ26:69~75
2025年3月30日(左近深恵子・レントⅣ)
主イエスは弟子たちと過越の出来事を記念する食卓を囲まれた後、祈るために彼らを伴ってオリーブ山へ行かれました。その時弟子たちに、「今夜、あなたがたは皆、私につまずく」と言われました。『私は羊飼いを打つ。すると、羊の群れは散らされる』と書いてあるからだと、預言者ゼカリヤの言葉も思い起こさせます。ゼカリヤはこの箇所で、罪深い民によって殺された神の民の牧者の死を語っています。神がお立てになった自分たちのための羊飼いを殺した、羊の群れなる民の罪は、神の怒りの剣となって民へと向かい、羊飼いを失った民は自らを散らされた者とすると。この箇所を主イエスは、ご自分の死と、弟子たちが散り散りになることに重ねて語られます。ゼカリヤが語る牧者を殺す民のように、弟子たちも主イエスを見捨てることによって、自分たちがバラバラになり、寄る辺ない状態で世の罪深い力に晒されることになります。けれどそこで終わりません。ゼカリヤ書は8節以降で、牧者を殺したエルサレムの民は、エルサレムに敵対する諸国によって2/3が殺され、1/3が残されると、残された民はその試練の中で金属が火で不純物を取り除かれるように精錬され、神様から「わが民」と呼ばれ神様を「主はわが神」と呼ぶ本来の在り方へと回復されることを語ります。主を見捨て、散り散りに残された弟子たちも、神様から与えられるその試練の火の中で精錬され、主なる神から与えられていた本来の関わりへと回復されることも、主はこの箇所を引用することで示されたのではないでしょうか。主は弟子たちに続けて、「私は復活した後、あなたがたより先にガリラヤへ行く」と言われます。主の羊の群れである彼らの道は、主が打たれ、主を見捨てて終わりではないと、主の死の先に復活があり、主と共に進む道が開かれることをも語ってくださったのです。
けれどペトロの反応は、まるで主の言葉の最初の部分しか聞いていなかったかのようです。自分たちが主に躓くと言われたことが受け容れられません。“生半可な覚悟でここまで従ってきたのではない”、そう思ったのでしょうか。“一番弟子の自分を他の弟子たちと一括りにされたくない、自分だけは特別だ”、そうも思ったかもしれません。「たとえ、皆があなたに躓いても、私は決して躓きません」と主張します。そのペトロに主イエスは「よく言っておく」と言われます。主イエスがこれから大切なことを言われる時のフレーズです。これから告げることは必ず実現されるのだと、だからしっかりと耳を傾けるようにと呼び掛ける言葉です。「よく言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言うだろう」と言われました。しかしペトロは、主イエスの言葉よりも自分のプライドを守ることに固執し、「たとえ、ご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません」と言い放ちます。ペトロらしい威勢のいい言葉ですが、そう思ったのはペトロだけではありません。「弟子たちも皆、同じように言った」とあります。彼らも、自分たちはそんな弱い者ではないと言い張ったのでした。
この時の弟子たちは、主イエスに従い通す自分たちの意志の強さに自信がありました。しかし実際に弟子仲間のユダの手引きによって、指導者たちが遣わした大勢の群集が、剣や棒を手に現れ、主イエスが捕らえられてしまうと、まるで羊飼いが打たれて散り散りになってしまう羊の群れのように、弟子たちは皆、主イエスを見捨ててバラバラに離れていったのでした。
主イエスは大祭司カイアファの屋敷へと連れて行かれました。そこには、主イエスを殺すために手を組んでいた律法学者や長老たちもいました。大祭司、律法学者、長老、彼らはユダヤの民の最高決議機関である最高法院を構成するメンバーです。共同体の公の機関が、主イエスに死刑判決を下す証拠を集めようと、形ばかりの裁きの場を急遽作ったのでした。
ペトロは他の者たちと同様、一旦は主イエスを見捨てて逃げましたが、そのまま去ってしまうことができなかったのでしょう。連行される主イエスの後を遠くからついて行き、主がどこへと連れて行かれるのか、どうなるのか、成り行きを見届けようと大祭司の屋敷まで来ます。「たとえ、皆が躓いても、私は決して躓きません」、そう言い張った思いは嘘では無かったのです。そうして屋敷の中庭まで入って来て、下役たちに紛れて彼らと一緒に座っていました。そこでペトロは試みに遭います。召し使いの女が一人近寄って来て、「あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた」と言います。主イエスが形ばかりとは言え公の裁判にかけられている同じ敷地の中庭で、公ではない、最高法院のメンバーでも何でもない一人の使用人の言葉に、ペトロは恐怖心を募らせます。主イエスが置かれている状況と対比して、ペトロの恐怖を過剰だと取る見方もあるでしょう。しかしキリストとのつながりから遠ざかると、人は羊飼いを失い、散らされた羊のように、孤独の中、この先訪れるかもしれない見えない未来に怯え、あらゆることに不安を掻き立てられるのです。
ペトロは、女の人が何の話をしているのか全く分からない振りをします。「皆の前で打ち消した」とあります。その女の人だけでなく周りにいる全ての人に、自分と主イエスの関係が知られてしまうことを恐れています。自分の答え方一つで、自分も屋敷の中の主イエスと同じような目に遭うのではないかと、恐れたのかもしれません。
ペトロはこれ以上問われることを避けようとしたのでしょう、中庭から門の方へと退きます。屋敷の中におられる主イエスとの間も開いてしまいます。しかしそこでも主イエスとの繋がりを問われます。今度問うてきた者は、直接ペトロではなくそこに居合わせた人々に向かって、「この人はナザレのイエスと一緒にいた」と言います。問いが人々の間に広まることを恐れて後退したのに、人々に問われてしまいます。ペトロは「そんな人は知らない」とつながりを否定します。問う者は「ナザレのイエス」と言っていますが、その名前さえ口にしない、強い否定です。
強く否定したのだからもう問われることは無いと期待したのでしょう。そこに留まっていたペトロですが、人々は放っておきません。今度は人々の方からペトロに近寄り、ペトロにガリラヤ地方の訛りがあるからナザレのイエスの仲間だと、根拠まで述べて主イエスとペトロの繋がりを主張します。訛りがあることがどれだけ証拠になるのか、人々にどこまで確信があって言ったのか明らかではありませんが、瞬く間にその場に居た人々の間でペトロに対する見方が固まってゆきます。ペトロは「『そんな人は知らない』と誓い始め」ます。一言否定して終わると言うより、一旦口にした否定の言葉を正当化しようと、躍起になって後から後から言葉を重ねる姿が思い浮かびます。必死に否定するあまり、呪いの言葉さえ口にします。誰に対する呪いなのか定かではありませんが、“もし自分の言っていることが嘘ならば自分は呪われたって構わない”、そのようなことではないでしょうか。恐れている状況にどんどん追い詰められ、自分を守ろうと必死になるペトロは、主イエスに従う道を見つめる目も失われています。主イエスが、ペトロは鶏が鳴く前に三度ご自分のことを知らないと言うと言われたことにやや憤慨しながら、自分は死なねばならなくなっても、決してあなたを知らないなどと言うことはないと断言したのはほんの数時間前のことです。その時、自分では認められなかった自分の中の弱さが、自分を捨てて主イエスに従う決意を挫けさせ、自分を守るために主イエスを何度でも否定してしまいます。ガリラヤ湖で漁をしていたペトロに、「私に従いなさい」と差し出してくださった時からいつも、主イエスはペトロの傍で手を差し伸べてくださってきました。その手に自分も弟子たちの誰よりも最初に手を伸ばして繋がった、弟子たちの中で最も長く繋がって来たことが、ペトロの誇りでありました。そうであるのに、主イエスの手を振り払って自分を守ろうとした弱さと頑なさは、ペトロだけのものではないことに、自分もその一人であることに、私たちは気づかされます。
弱さにも色々あります。体が強いか弱いか、といった弱さもありますが、主から離れ出ることへとひきずられる弱さがあります。そのような弱さは罪から来ます。パウロもローマ書で、罪を弱さと言う言葉で言い換えています。私たちが抱える問題の大半は、初めから自分の意思で主イエスから離れてゆくよりも、弱さによって離れてしまう、弱さによって従いきれないということが大半なのではないでしょうか。主に従う者でありたいと願っているから、実際には離れてしまっていることになかなか気づきません。敢えて気付こうともしません。自分の現実を検証しても仕方が無いのだと、開き直ることに寧ろひきずられるかもしれません。迷い出た羊は自力では、羊飼いの所に戻れません。ペトロに、主の手を振り払って、どんどん主から遠くなっていたことに気づかせたのも、ペトロ自身ではなく主イエスの言葉でした。
鶏の泣き声によって、ペトロは主イエスの言葉を思い出します。自分を自分で守らねばと頑なになっていたペトロの内側に、主イエスの言葉が突き刺さります。もはやそれ以上、人々に主イエスとの繋がりを否定することができなくなります。主を否定する言葉を発し続けていた場所から外へと逃げ出します。口を噤んだペトロの内側に、主の言葉が一層深く刺さります。自分は、主イエスが言われた通り弱い者であったことに気づき、泣き出します。主イエスが差し出してくださった手を振り払い、そんな手を取ったことも無いような振りをし、手を取った者は自分では無いと言い張った自分に気づきます。主イエスが語られたたとえ話の中の放蕩息子は、父親から離れ、父親の財産を全て浪費し、人間として生きることができなくなって、父親の家を思い出して初めて、我に返ります。ペトロも、主イエスから離れ、主との繋がりを自ら失い、主の弟子として生きることができなくなって、主の言葉を思い出して初めて、我に返ります。我に返るとは、主と離れたところで自分自身に返ることではなく、主との繋がりの中にある自分に帰ることであるのです。
今日の箇所に主イエスは登場しません。スポットライトを浴びているのはペトロだけのような場面です。しかし出来事の背後に主イエスがおられます。大祭司の中庭から門へと、門から外へと、ペトロが移って行く。その奥で、ペトロよりもはるかに厳しい状況で裁きの場に立っておられる主イエスの苦しみがあります。ペトロや他の弟子たちの弱さをずっと見つめてこられ、躓いた後、彼らが再びご自分に従う道を歩み出せるように、彼らの躓きとご自分の復活を告げられ、彼らの罪の赦しのために、囚われの身となり、偽証が次々と立てられる不当な裁きに身を置いておられる主イエスがおられます。
ペトロは自分の弱さを認められなかったのに、主イエスはペトロの弱さをご存知でした。にもかかわらず、“私を知らないと繰り返すお前とはこれまでだ”と関係を切るのではなく、復活したらガリラヤへ先に行っていると言われました。ご自分から離れ、散り散りに去る者たちと、死を超えて共に居てくださる方であることを教えられました。その主の言葉を思い出したペトロは、激しく泣きました。み言葉が自分の弱さに突き刺さる者の激しい痛みと苦しみがあります。しかし、このように泣くことのできる安らぎと幸いに代われるものはありません。
絶望する時、心の底から泣くことは難しいものです。自分に期待する自分の像と、現実の弱い自分の間で流す涙もあります。しかし、この痛み、苦しみ、愚かさを、自分以上に知っておられながら、自分のために祈られ、自分をも救うために命をささげてくださる方がおられると知る時、心から安心して涙を流すことができます。死を超えて共におられるこの方の傍でなら、もう自分で自分を守ろうと頑なになる必要も無いので、全てを注ぎ出して泣くことができます。
今日の出来事を、この福音書だけでなく、マルコもルカもヨハネも伝えています。主イエスがエルサレムで受けられた苦しみと、主イエスがそこで何を語られ、何を為さり、何を担われたのか伝えることが中心の受難物語において、ペトロの出来事にこれだけ紙面を割いています。使徒たちも、福音書の書き手たちも、それを伝える教会も、この出来事を重く、重く、受け止めて来たからではないでしょうか。「あなたこそメシア、生ける神の子です」と信仰を言い表したその告白を、主イエスから「岩」だと、「その上に私の教会を建てよう」と言われた、教会の中心的な人物であるペトロです。そのペトロが、他の弟子たちと同様、結局主イエスから離れてしまったことを、どの福音書も大切に伝えています。「ご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません」と断言する勇ましさにおいて、主イエスに対するペトロの熱意は頂点に達したかのようです。その同じ晩に、主イエスを徹底的に否み、この一番弟子は闇の中に落ちてしまいます。その奥底から主イエスのみ心へとみ言葉によって立ち返ることができた、それが教会を代表する使徒ペトロなのだと、教会は伝えてきました。
かつて主イエスはこう言われました、「誰でも人々の前で私を認める者は、私も天の父の前で、その人を認める。しかし、人々の前で私を拒む者は、私も天の父の前でその人を拒む」(10:32~33)。この主の言葉に慄かずにはいられない私たちです。主イエスは大祭司の館で、ご自分を殺すために裁きを捻じ曲げる指導者たちの前で、ご自分が神の子、メシアであることを否定されず、寧ろ人の子の到来を告げる聖書の言葉を引用されます。その同じ頃、ペトロは中庭や門の傍で主イエスとの繋がりを幾度も否みます。このペトロも、ペトロに自分を重ね見ずにはいられない私たち一人一人も、キリストの十字架によって闇の底から救い出され、頭なる主に繋がっています。自分の意思の力と自分の熱量で歩んでいるのではなく、イエス・キリストの十字架の死と復活によって罪の赦しが与えられているのだと、み言葉によって繰り返し刺し貫かれ、そのような恵みが自分に与えられていることに驚きを新たにされ、イエス・キリストへの感謝を新たにする者たちの群れが教会なのだと、教会はこの出来事を大切に語り伝えてきました。「私の後に従いなさい、私と共に行こう」、そう招いてくださったイエス・キリストに導かれる人生でありたいと願い、自分のこの願いも、願い通りに行動することのできない自分の弱さも、主の恵みの中にあることに信頼し、共におられる主に全てを注ぎ出して、またここから主の道を歩み出したいと思います。