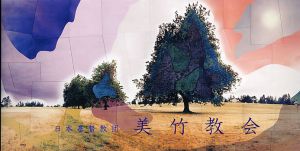「裏切る人々のために」出エジプト12:21~28、マタイ26:17~25
2025年3月16日(レント・左近深恵子)
受難節は、主イエス・キリストが私たちのためにお受けになった苦しみに思いを深める時です。主イエスがエルサレムの都にろばの背に乗って入られてからのことを聞いています。主は金曜日に十字架にお架かりになります。その前夜の出来事を今日は聞きました。最後の晩餐としばしば呼ばれる場面です。確かに主イエスが十字架に命を捧げられる前に最後に弟子たちを共にされた、別れの食事です。しかしルカによる福音書やヨハネによる福音書は、復活された主イエスが弟子たちを訪ねられ、何度も彼らと食事を共にされたことを伝えています。この晩食卓でされたように、パンを取り、割いて弟子たちに分け与えられる主イエスから弟子たちは受け取り、パンを噛みしめながら、かつて復活されると約束された主イエスの言葉を思い起こし、本当に主イエスは復活されたのだと、生きておられるのだと喜びも味わったことでしょう。私たちが聖餐の食卓で聴く、「取って食べなさい。これは私の体である」「この杯から飲みなさい。これは、罪が赦されるように、多くの人のために流される、私の契約の血である」、これらの主の言葉も、この晩主が言われた言葉です。この言葉を聖餐の食卓から聞き、キリストの体と血をいただき、そうして新しい命に生きることができることができる、そのために主が受けられた苦しみがあることを思います。
この食事は、出エジプトの出来事、とりわけ先ほど共にお聞きした箇所を含む「過越」の出来事を記念して行う、過越の祭と呼ばれるユダヤの民にとって最大の祝祭の一部でした。親族や親しい人々と囲み、神さまの救いの恵みと、神の民としての出発を思い起こし、神さまに感謝をささげる、1週間にも及ぶ祭の中の特別な食事でした。除酵祭も、エジプトを発つ日の食事において、急いで出発しなければならなかったために、パン生地に酵母を入れて発酵させている時間が無く、酵母を入れないでパンを焼いたことを記念する祭で、過越祭と一緒に祝われました。
主イエスは26:2で弟子たちに、この過越祭で、十字架につけられるため、ご自分が引き渡されると告げておられました。その頃民の指導者たちは、大祭司の家に集まってまさに主イエスを殺す相談を始めていました。その時点で指導者たちは、祭の間は民衆の中に騒ぎが起こるから主イエスを捕らえるのは止めておこうと考えていました。しかしその後、12弟子の1人ユダがかれらの所にやって来て主イエスを引き渡す取引を持ち掛けたことで、状況は変わります。ユダは指導者たちから見返りを受け取り、主イエスを引き渡す機会をうかがい始めます。主イエスを殺そうとする勢力とユダが結託した今、彼らが主イエスの命を奪う力もその時を決める決定権も握っているかのように見えます。しかし主の時を決めるのは彼らではありません。「二日後の過越祭」に「引き渡される」と宣言された主の言葉の通りに、イスラエルの民をファラオの支配から導き出された神さまの救いの祝いの日に、神さまが新しい過越しをもたらされ、神のみ子ご自身がその犠牲となられるのです。
除酵祭の第一日に、主は弟子たちに命じて、エルサレムの都の中のある人の家に、過越の食事の準備をさせます。ご自分がその時引き渡されると告げられた祭のために、今や「私の時は近づいた」と告げて支度をさせます。過越しの食事も、この時も、その主は指導者たちでもユダでもなく、主イエスであります。主はご自分の命を狙う者たちがあちこちに潜む都で、迫り来る死を見つめながら、神様の救いのみ業を記念する宴の席を弟子たちのために整えられるのです。
食事の席で主は12弟子に突然、「あなたがたのうちの一人が私を裏切ろうとしている」と言われます。「裏切る」と訳された言葉は本来、「裏切る」を意味しません。一般に裏切りを意味する言葉は他にありますが、それは新約聖書で一度しか用いられていません。ルカによる福音書で12弟子を主イエスが選ばれた場面で、ユダのことを「後に裏切り者となった」と述べる時だけです。今日の箇所で「裏切る」と訳された言葉は、誰かに、あるいは何かに、与える、渡す、という意味の言葉です。26:2で「引き渡される」と主が言われたのがこの言葉です。これまで弟子たちに繰り返しご自分の受難を予告してこられましたが、その度にこの言葉で「引き渡される」と言われてきました。主イエスの受難と死は、人が主を「引き渡す」ことによるのです。それを実行に移す者があなたがたの内の1人だと、主は弟子たちに言われたのです。
指導者たちが主イエスを殺そうとしていることを、弟子たちは知っていました。主イエスを捕らえようとする手が、いつどこから伸びて来るか分からない、そのような状況にあります。その手に主イエスを引き渡してしまうことに、ユダ以外、一切関わりがなかったなら、主イエスはこの時弟子たち皆にこのことを告げることはされなかったのではないでしょうか。この時弟子たちも、主の言葉に対し「それはユダのことですよね」と言うわけでも、こっそりユダの方を見るわけでもなく、皆心を痛めて、「主よ、まさか私のことでは」と、次々と主イエスに問うています。ユダが突出して主を引き渡す可能性を抱えていたとは言えないのです。「私に付いて来なさい」と主に呼び掛けられ、主の後に従う弟子となった12人です。主イエスとの出会いを与えられ、自分のこの先の人生を、神さまが遣わされた方にすべて委ねられる幸い、その方に属する者とされて生きることのできる幸いの中に導き入れられてきた人々です。その主を引き渡すということは、主との繋がりを切り離すということです。引き渡す相手の方が主に勝るとし、自分が主に属する者であることを否定するということです。「私に付いて来なさい」と差し出してくださった主の手を振りほどき、主を自分の主としなくなることです。弟子たちは“この私はそうしませんよね、私のことではないですよね”と、主が“あなたのことではない”と否定してくださることを期待して、主に縋ったのでした。
答えを求める弟子たちに主は、「私と一緒に手で鉢に食べ物を浸したものが、私を裏切る」と言われます。過越の食事で、最初の杯の後に、フルーツやナッツにスパイスやぶどう酒、もしくはぶどう酢を加えて作られたジャムのようなものの中に野菜を浸して食べることをしたと言われています。12弟子は同じようなタイミングでそこに浸していたことでしょう。一人を特定するためではなく、この特別な食事を囲む主イエスに最も近い弟子たちの中から、主を引き渡す者が出ることを言われたのではないでしょうか。
続けて、その者が引き渡すことによってご自分は去って行くと、しかしそれは、聖書に書かれていることの成就なのだと言われます。主なる方を自分の主とし続けられない人間の罪が、神のご計画を阻んでしまい、主イエスは去らなければならなくなるのではありません。人の罪によっても神さまのご計画は阻まれない、み言葉は破棄されないのだと、ご自分が去るのは神さまの救いのご計画によるのだと告げられます。
しかし、だからと言ってユダの罪が帳消しになるのでも、軽くされるのでもありません。「人の子を裏切る者に災いあれ」と言われます。この「裏切る」と訳された言葉も、「引き渡す」という言葉です。主イエスを引き渡す者に対して、「災いあれ、生まれなかった方が、その者のためによかった」と言われます。衝撃的な言葉です。「生まれなかった方がよかった」、そのような言葉をもし親が子どもに言ったとしたら、その親は親としてふさわしくない者だと非難されかねない、それほどの言葉ではないでしょうか。この言葉に抵抗を覚え、“ユダをそのような人間にした神さまが、創造主としてふさわしくないのではないか、ユダにそのような思いを抱かせたまま放置している主イエスが、ユダを導く者としてふさわしくないのではないか”、そうユダの肩を持ちたくなる思い、神さまや主イエスにも責任があると考えたくなる思いが、沸き起こるかもしれません。
主イエスを引き渡す見返りに銀貨30枚を指導者たちから受け取っているユダを、サタンの化身のように見る解釈がされてきました。ユダには主イエスを死の危険に追い詰める何か理由があったのだと、ユダも仕方が無かったのだと、ユダの動機に配慮し、好意的に見る解釈も為されてきました。いずれにしても、ユダは主イエスを引き渡そうと考え、既に行動を起こしています。どうユダを解釈しても、ユダが主イエスを引き渡す者となります。主イエスを引き渡す者の第一号となります。最も近しい者たちで囲む、神の民として最も大切な食卓に、その近しさを利用して主イエスを引き渡そうとしている者がいる、第一号とならずとも、皆「まさか私のことでは」と動揺するしかない者たちである、この事実に最も苦しんでおられるのは主イエスです。神さまが遣わされた救い主を引き渡す罪は死に値するのです。この罪の重さを「生まれなかった方が、その者のためによかった」と、主イエスは12弟子皆に告げます。しかしユダはその主に、ほかの弟子たちと同じ言葉で、「まさかわたしのことではないですよね」と言います。それが自分であることに気づかない振りをして、自分の罪を他の者たちと同じ言葉で覆い隠します。しかしユダは主イエスに対して、他の弟子たちとは異なる呼び方もしています。「主」ではなく「先生」と呼びます。一般にユダヤ教の教師に対して教えを求める者たちが用いる呼び方です。主イエスをもはや自分の主としていないユダの内側が現れているようです。主イエスとの間に距離を置き、教師の1人に過ぎない者であるかのように「先生」と呼び、“あなたが言っているのは私ではないですよね”と言ってしまう。そのユダに主イエスは「あなたがそう言ったのだと」言われます。どのような意味で言われたのか、様々な受け止め方が可能な、意味が明らかではない主イエスの言葉です。ただ、引き返すこともできる自由がありながら、その道を閉ざすような言葉を発したのはあなたなのだ、そう言われているように思います。主イエスを引き渡すのではない道、主を自分の主とし、もし主イエスに従う苦しさがあるならその苦しさを主に注ぎ出す道があるのに、ユダは本当の自分を主から遠ざけ、他の弟子たちと同じ言葉で取り繕った自分を彼らの中に紛れ込ませ、主を引き渡す道を自分に残しました。このユダの罪の重みは死に値するのです。
人は罪を犯すために生まれて来るのではありません。自分のただお一人の主を、自分の主ではないと自分から切り離すため、自分の真の羊飼いを自分の羊飼いでは無いと拒むため、そうして自分で自分を寄る辺ない者とし、飼う者のいない羊のようにし、生きる道を自ら失ってしまうために生まれてくるのではありません。天から降られ、迷っている羊のようなご自分の民を一人一人尋ね求め、私の後に従いなさいと手を差し伸べ、天からのマナとなり、生ける水となり、その人が真に生きることができる道へと導いて来られた主イエスは、ご自分の群れがご自分の手を払いのけ、自ら死の陰の方へと突き進んで行くことに、苦しんでおられます。主の受難の苦しみとは、慈しみを注ぎ、み言葉を与え続けてきた人々、とりわけ日々愛を注ぎ続けてきた者たちが、ご自分との関わり、ご自分がこれまで注いできたもの全てを否定し、罪に支配され、罪が行き着く先の滅びの死へと沈んで行くことの苦しみです。「人の子を裏切る者に災いあれ」、この言葉を主イエスはこれまで何度も言われてきました。多くは民の指導者たちの偽善に対してでありましたが、18章では弟子たちに言われています。天の国では一体誰が1番偉いのかと言い合い、他者よりも自分が上に居られるよう、主イエスに認めてもらおうとする弟子たちに対し、主は1人の子どもを呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせます。そして、「心を入れ替えて子どものようにならなければ、決して天の国に入ることはできない、子どものように自分を低くする者が天の国で1番偉いのだ、私の名のためにこのような子どもの1人を受け入れる者は、私を受け入れるのである」と言われます。そして続いて、「人をつまずかせるこの世に災いあれ。つまずきは必ず来るが、つまずきをもたらす者には災いがある」と警告されました。その警告と同じ言葉遣いで、主イエスを引き渡す者を「災いあれ」と言われたのです。主がこうあってはならないと教えてこられたのに、その道を進んでしまう者を「災いあれ」と言われたのです。
「災いあれ」と訳された元の言葉は、警告する時に用いる言葉でありますが、痛みや嘆きの感情や反応を表す、自然に口をついて出て来るような言葉でもあります。日本語にすれば「ううっ」「ああっ」といった言葉です。主イエスはご自分を引き渡そうとしている者を見つめ、痛み、嘆き、呻いておられるとも言えます。ユダは主を遠ざけましたが、主は遠くからユダを呪っているのではありません。呻き嘆きの言葉としてこの部分を直訳すると、「人の子は去って行く、彼について書かれているように。ああっ、しかし、人の子を引き渡すその人よ」、そのように訳すことができます。主の苦しみの深さを思わされます。
私たちは主の苦しみを見つめることに徹することができない者です。私たち自身も、主を主とし続けられなかった覚えのある者だからです。そうでありながら、私たちを奥底まで見つめておられるキリストのみ前ですら、“あなたを引き渡すのはまさか私ではないですよね”と言って、自分を誤魔化そうとしたくなるのです。主の手を振り払い、主が自分の主であることを退け、自ら滅びへと進んでしまう私たちのために、キリストが滅びの道へと進んでくださいました。私たちが負うべき罪の値を代わりに負うために、十字架へと向かってくださいました。与えられた命と、導き入れられた救い主に従って歩む生涯を、罪に開け渡してしまう一人一人を、その人に命と生涯という時を与えてくださった方が見つめなければならない苦しみ、「産まれなかった方が良かった」と呻かずにはいられない苦しみを、主イエスは苦しまれました。その苦しみを抱えながら、過越の食卓を準備させ、引き渡す弟子と共に食卓を囲み、その者と共に鉢に食べ物を浸されました。呻きながら、「取って食べなさい。これは私の体である」と過越のパンを分け、ご自分を引き渡す者たちを救うために、十字架に命を捧げてくださいました。
私たちが償うべきであった罪の値、私たちが受けるべきであった苦しみを、主が代わりに負ってくださり、神様はキリストによって赦しを与えてくださいました。だから私たちは復活の主によって力をいただき、自分の闇を見つめる力をいただいています。「主よ、まさか私のことではないですよね」ではなく、「それは私です」、そう答えることができる者とされているのです。