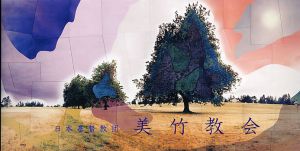「主に香油を注ぐ人」申命記6:4~6、マタイ26:6~13
2025年3月9日(左近深恵子)
先週の水曜日から、受難節(レント)に入りました。既に私たちは1月から、主がエルサレムで過ごされた最後の1週間を伝える聖書の箇所に耳を傾けてきています。主は神殿の境内で人々に、これまでのように天の国について語られました。特に、ご自分が再び来られる時に天の国が完成されることを語られました。そして、教えを語り終えられる時、「人の子は、栄光に輝いて天使たちを皆従えて来る時、その栄光の座に着く」と言われています(35:1)。主が再び来られる終わりの時に、主を包むのは栄光の光である。主が座するのも栄光の内であることを語られました。その栄光の光に包まれた天の宴の席に、主は私たちを招いてくださることを語られました。聞き手の弟子たち、そして私たちの今を、自分の目に映るものを映るように見るだけでなく、終わりの日に明らかになる栄光から見ることを教えてくださいます。そして主は言葉を続けられます。ご自分が二日後の過越祭に、十字架につけられるために引き渡されるとの言葉です。全く光に馴染まない、暴力と血、敵意と苦しみが、主に襲い掛かる現実を主は宣告されたのです。
主イエスはエルサレムに来られる前からこれまで、既に三度に渡ってご自分が民の指導者たちから苦しみを受けて殺されることを弟子たちに告げて来られました。苦しみと死だけでなく復活されることも必ず告げておられました。しかし、彼らの目の前で主イエスが捕らえられ、殺される瞬間が二日後に迫っているこの時、主イエスは十字架に焦点を絞って告げられます。目に見えることだけで決めつけ、絶望に陥っていくであろう弟子たちに、十字架に向かって行かれる方は、栄光の内に再び来られることを約束された方であることを心に刻み付けるようにと、ご自分が見据えている十字架を共に見るようにと、呼び掛けておられるようです。この方が苦しまれ、死んでくださること無くして、弟子たちも私たちも、栄光の光の内に招き入れられることを願うことはできないのです。
ご自分の死を主が予告されていた頃、主の言葉通り、主イエスを十字架に追いやろうとする勢力は結託して、主イエスを捕らえ、殺す相談を始めました。彼らが集まったのは、神殿で最も力を持つ大祭司の家でした。他に相談しなければならないこと、力を尽くさなければならないことがいくらでもあったはずの指導者たちです。彼らが牧すべき群れがあったはずです。しかし彼らは主イエスを殺すために集まり、失敗無く殺すために実行のタイミングを相談していたのです。
主イエスは指導者たちが何をしているのかご存知であったでしょう。しかし主は指導者たちの企みを阻止することなく、糾弾することもなく、弟子たちを伴って、べタニアと言うエルサレム近郊の村に住んでいるシモンの家におられます。21章には、主イエスがエルサレムの都に入られたその日、夜はベタニアに泊まられたことが記されています。ベタニアから毎日、都に来ては語られていたのでしょう。
ベタニアのシモンは既定の病を患っている人でありました。既定の病とは、律法で清められることが必要と定められている病でありました。その病を負う人は、誰かと接触することで、その人も清めが必要な者となってしまわないように、他者との交流を避けなければなりません。他の人から避けられ、遠ざけられがちな人の家に、主イエスはおられました。これまでそうしてきたように、この時も神の民の群れから距離をおかなければならなかった人と共におられ、皆が避けて来たその人の家の客となり、その家に祝福をもたらしています。ご自分の命までも呑み込もうと迫る闇を見つめながら、主はこれまで為してこられたことを静かに続けておられます。
おそらく食事の席であったのでしょう。そこに一人の女性が現れます。同様の出来事が他の福音書にも記されていますが、マタイによる福音書はその婦人の名前も何も記しません。この福音書の関心はこの婦人の人物像にありません。主イエスの方へとその人が近づいて来た、その人は香油の壺を持っていた、そしてその香油を主イエスの頭に注いだと、その人の行動を述べてゆくだけです。その間、女性の言葉も主イエスの言葉もありません。主イエスはこの婦人を制することなく、静かに受け止めておられます。福音書は、この人がしたことを大切に伝えています。
香油はもてなしの場で用いられ、宴の始まる前には香油を塗るということがあったのだそうです。香水のようなものですから少しの量でしょう。しかしこの婦人は塗ったのではなく、注ぎかけたのです。当時の食事のスタイルで横たわって食卓に着いておられた主イエスの頭に、おそらく壺の中の香油を全て注ぎかけたのです。
無言のうちに進められる香油注ぎ。部屋に充満したであろう高価な香油の香りが、聖書から立ち静かに立ち上ってくるような、印象深い場面です。この場面の静けさを破るのはこの福音書では弟子たちです。弟子たちは憤慨します。極めて高価な香油を注ぎ出すというのはやり過ぎだ、それは無駄遣いだ、売れば貧しい人々に施すことができたのにと、女性の行動を非難します。
時と場所が違えば、弟子たちの主張に賛同する人は多いでしょう。衣食住に事欠く貧しさの中にある人々に助けの手を差し伸べることは、律法でも求められている、善い行いです。高額な値で売れる極めて高価な香油を、たった一人の人に、たった一度のために使い切ってしまうのは浪費だ、その金額で大勢の人を助けることができるという主張は合理的だと、困窮している人のことを真剣に考えれば、弟子たちの方が正しいと、多くの人が考えるでしょう。
しかし主イエスは弟子たちを遮り、この女の人は私に良いことをしてくれたのだと言われます。ご自分を殺す相談をするために集まっている民の指導者たちのことは止めずにおられる主イエスが、この弟子たちの振る舞いは止められます。この婦人は、指導者たちの手で死に引き渡される主イエスの葬りに備えているのだと、主は言われます。婦人本人におそらくそこまでの意図は無かったでしょう。しかし主イエスが十字架に架けられ、死なれた後、アリマタヤのヨセフは急いで埋葬することになります。安息日が始まろうとしている金曜日、遺体に油を塗るような丁寧な葬りはできません。この婦人は先立って、葬る準備をしてくれたのだと言っておられるのでしょう。
指導者たちは、主イエスを排除すれば、自分たちの立場を守ることができると思っています。主イエスに死をもたらすことが、主イエスの言葉や業を無かったことにし、自分たちのこれまでの在り方をこのまま続ける道を守れる、主イエスに勝利できる道だと思っています。自分と同じように主イエスの言葉と力と存在を消し去りたい者たちが居ることに意を強くし、互いの違いも超えて死の力の下に一つとなっています。
しかし、死の危険が迫るエルサレムから去ろうとせず、病み、共同体から遠ざけられた者の家の客となって留まり続けるこの方を、この婦人は敗北者と見ていません。危機の中にあっても、敵対者が奪うことのできないものがこの方にあることを知っていたのでしょう。この婦人はこれまで、主の言葉、主の業によって何かをいただき、感謝をしてきたのでしょう。
主イエスに対して敵対者たちは敵意を募らせています。主イエスに感謝をしている人々、主イエスを神が遣わされた方と信じる人々にとって、不条理な敵意です。神さまのみ心に反する、個々の人間の力では止めようの無い大きな流れが主イエスを呑み込もうとしています。答えが見えないこの深い闇の中で、この婦人は主イエスの傍に自分が居ることを望みました。迫る危機から主イエスを守る力は自分に無いけれど、この闇の中に留まっておられる主イエスに信頼していました。神さまがこの状況に示してくださる答えはこの婦人にまだ明らかではありませんが、主イエスが神さまの答えであることに信頼していたのでしょう。それは言い方を変えれば、闇の先に主によってもたらされる栄光の光があることに信頼していたということではないでしょうか。
弟子たちが主張しているような施しを困窮している人々にしたら、主イエスも喜ばれるでしょう。貧しい人への施しだけでなく、律法に定められている、隣人を愛する行いをしたなら、主イエスはそれも喜ばれるでしょう。それらをしないとこの婦人が言っているわけではありません。主イエスはそれらをしなくて良いと言われているのではありません。貧しさによる苦しみが地上から消えることは、残念ながらこの先も無いでしょう。必要を欠く隣人の困窮のために何かをする機会はこれからもあり続けます。しかしこの人にとって主イエスに何かをできるのはこの時しかなかったのです。そしてこの人にとって主イエスは、あらゆるものに勝る方です。危機の中にあろうと、死がこの人に迫ろうと、主であることに変わりない方です。主イエスに危機をもたらす人々の力に勝る方であります。守る力は差し出せないけれど、自分にできる最大限のことを主のために捧げたいと願った。だから最大限高価な香油を捧げたのでしょう。香油を一度に全て注ぐことが常軌を逸していることは、この女の人も良く分かっていたことでしょう。しかし香油の全ては、自分を丸ごと捧げるしるしであったのではないでしょうか。
貧しい者に施しができたのにと憤慨した弟子たちは、神様を愛することに基づいて主張したのでしょうか。エルサレムに来る前に、ペトロは弟子たちを代表して、主イエスのことを、「メシア、生ける神の子です」と言うことができました。彼らはその信仰に立って、婦人を非難したのでしょうか。彼らは律法に定められた善い行いを、何かを手に入れる手段にしてしまってはいないでしょうか。施すことのできた人数の多さという成果で、自分や他者の行いの価値を測ろうとしていないでしょうか。
先ほど申命記6章から聞きました。そこに記されているように、私たちの神となってくださった、唯お一人の神であり主である方を、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして愛することを律法は求めています。自分を丸ごと注ぎ出すように神さまを愛することが、律法の土台であります。この土台から離れて何かを行うことは、神さまが律法によって求めておられることを守ることにはなりません。この女の人は、神さまが遣わされた主イエスに、おそらく自分の全財産と言える高価な香油を捧げました。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、神さまが遣わされた方に捧げました。それは神さまへの愛から溢れ出した行いでした。律法は様々な行いを求めています。しかし、主イエスに自分を捧げること、神さまを愛することは、律法に求められている多くの行いの中の一つではありません。それらの源となるものです。善い行いをすることと、神さまを愛し主イエスに自分を捧げて礼拝することのどちらを優先するのか、という選択はあり得ないのです。
主イエスは今日の箇所の少し前で、人々に教えを語られた最後にこうも言われています、「あなたがたは、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていたときに飲ませ、よそ者であった時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気のときに世話をし、牢にいたときに訪ねてくれた」(マタイ25:35~36)。衣食住の貧しさも、人との関りの貧しさも含め、様々な貧しさが地上にあります。主に愛の業を捧げるために、隣人に何かを為すことを、主は喜んで受け止めてくださり、祝福してくださるのです。
この婦人は、何かを手に入れるために香油を注いだのではなく、主に対する感謝から主の傍へと進み出て、自分を全て注ぎ出すように香油を注ぎ出したのです。捧げられることが喜びであり、捧げたことでどうなるかなど眼中に無かったでしょう。この人の捧げものに、主がご自分の葬りの備えという新しい意味を与え、高めてくださったのです。状況が見通せなくても、答えが見出せなくても、神さまへの愛から捧げるものを、主は人の思いを超えたものへと新たにし、用いてくださるのです。
今日の箇所の出来事は、民の指導者たちが大祭司の家で主イエスを殺す相談に明け暮れている出来事と、12弟子の1人であるユダが主イエスを裏切って指導者たちに主イエスを売り渡す取引をした出来事の間で語られます。結びつくはずのなかった指導者たちの罪と、弟子の罪が、主を殺すことにおいて手を結び、一層大きなうねりとなり、闇が濃さを増すその狭間で、一人の婦人の捧げものが語られます。闇に呑み込まれない香りを静かに放ちます。主イエスがお生まれになった時、お生まれになったばかりの王に捧げるために宝を携えて、遠い東の国から学者たちが来ました。星とみ言葉に導かれ、キリストのもとに辿り着いた学者たちは、主のみ前にひれ伏して礼拝し、一人は乳香という貴重な香油を捧げました。そしてキリストが死を前にされた時、一人の婦人が香油を携え来て、跪き、捧げたのです。
神さまのみ心から離れ出た人の闇が引き寄せ合い、主イエスを殺すことへと大きく動き始めた時、主イエスはその闇の中に留まり続けられ、十字架の死へと進んでくださいました。このことを主イエスは今日の箇所で「福音」と呼ばれます。福音と聞くと大抵の場合、主イエスのご生涯と主によってもたらされた救い全体を思います。しかし死を目前にして、神さまに見捨てられた光が全く無い死の中へと向かわれる方が、答えの無い沈黙の中で十字架につけられ、十字架に留まり続けてくださる方が、ご自分の苦しみと死を経て為される御業を福音と呼んでくださいます。死にて葬られ、神さまがおられない陰府にまで降られ、そのところまでも神さまが共におられるところしてくださった闇を、見つめることへと促されます。キリストが復活の命の初穂となられ、終わりの時にもたらしてくださる栄光の光に照らされなければ、私たちには見つめることもできない闇を、キリストが共に見つめるようにと呼び掛けられます。そして、この福音が語られるところでは、名も無き一人の婦人のした行いもいつまでも語り伝えられるだろうと言われます。たった一人で為した大胆な行い、非難をされても迎合することの無かったひたむきな行いを覚え、自分もこの人のようでありたいと私たちも胸に刻むのです。