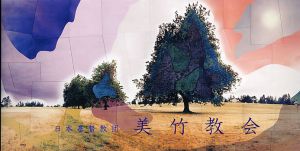「宝を預かって」イザヤ52:7~10、マタイ25:14~30
2025年3月2日(左近深恵子)
今日も、主イエスがエルサレムの都で人々に語られた教えの1つに耳を傾けます。主イエスは、ご自分の民、特にその指導者たちから苦しみを受け、死に渡されることをご存知の上で、ご自分の生涯最後となる過越しの祭りをエルサレムの都で祝うためにエルサレムに来られました。過越しの祭りを祝おうとやって来た大勢の人で賑わう神殿の境内で、日々語られました。マタイによる福音書の23章以降に、その教えがまとめて記されています。24章から25章には3つの譬えがあります。忠実な僕と悪い僕の譬え、先週夕礼拝でお話しした十人のおとめの譬え、そして今日のタラントンの譬えです。どれも天の国を、つまり神様のご支配を表すものです。どれにも、待つ人々が登場します。主人の帰りを待つ僕たちや、花婿の到着を花嫁の家で待つおとめたちです。神さまはそのお力をもって人々を導いてこられたことを旧約聖書は伝えます。そのご支配はイエス・キリストによって決定的に到来したことを、そしてキリストが再び来られる時に神さまのご支配は成し遂げられることを新約聖書は伝えます。そのキリストの到来までどのように待つのか、主イエスは譬えを通して教えておられます。
主イエスはこれまでも天の国のことを語り続けてこられました。しかしご自分の死がすぐそこまで迫っているこの時、人々に伝わって欲しいとの願いは一層増していたことでしょう。聴く人々も、主イエスが都の指導者たちから敵視され、主イエスを排除しようとする動きが起きていることを知る者は多かったでしょう。ただ人々には、このイエスという方なら特別な力で自分の行く手を遮るものを退けられるのではないか、そうやって自分たちを率いる存在となってくれるのではないかという期待があったのではないでしょうか。それができなければこの人の活動は失敗に終わり、逮捕され、場合によっては殺されて終わりだと。そして、主イエスはこの週のうちに捕らえられ、殺されます。人々は、死が彼らのもとから主イエスを奪ったと思うでしょう。やがて三日目に復活され、その後昇天され、聖霊が降られます。人々はまたも主イエスをその目で見ることも、その声を聴くこともできなくなったと思うでしょう。主イエスは目の前の人々に、その時あなたがたはこう待ちなさいと譬えで語られます。私たちを含む後の時代の人々に、キリストの再臨を待ちながら生きることを語られます。
今日の譬えは、直前の10人のおとめの譬えで最後に主イエスが言われた言葉を受ける形で始まっています。主イエスは「だから目を覚ましていなさい。あなたがたはその日、その時を知らないのだから」と言われます。そして訳出されてはいませんが、「なぜなら」という言葉があって、今日の箇所が始まります。キリストの再臨がいつであるのかあなたがたは知らないのだから、いつ来てもよいように信仰の目を覚ましていなさいと、なぜならあなたがたは主人から財産を託されている僕のような者であるのだからと、この譬えを語られるのです。
譬えは旅に出る主人が三人の僕に財産を預けるという話です。主人は天に昇られたキリスト、主人の僕はキリスト者たちと言えます。譬えは主人が不在の状況を描きます。しかし神さまが聖霊を遣わしてくださっていますので、主が不在とは言えないのが私たちの状況です。聖霊においてキリストが共にいてくださるけれど、キリストの姿を見たり、その声を聞くことができなくなる人々に、主人から財産を託された僕たちの譬えを語られます。
主人は自分の財産を一人一人に預けます。これはそれぞれが自分の財産をどう増やしたのか、増やせなかったのか、という話ではありません。僕が託された財産は主人に属しており、それを元手に増やしたものも主人のものです。主人は帰宅すると僕たちに預けた財産の清算をします。再臨のキリストのみ前で一人一人が主の宝をどのように用いてきたのか問われるのです。この譬えを、世界の経済格差を肯定する発言などと受け止めるとすればそれは見当違いということになるのです。
主人は僕に自分の財産を託します。財産を託せるほどに僕たちが有能であることを知っており、信頼しています。財産の単位はタラントンで表されます。1タラントンは6,000日分の賃金に相当します。人が生活しながら貯められるような額ではなかなかありません。それでも主人は僕に託した2タラントンや5タラントンを「僅か」と言っています。この譬え話の伝承の初期の段階で、単位がもっと少額だったからではないかとも言われています。そのような背景もあるのかもしれませんが、主が私たちに注いでおられるものの豊かさを思えば、わたしたち一人一人に託しておられるものはその豊かさの一部だということではないかと思います。かつて主は山上の説教で、「あなたがたは地の塩である」「あなたがたは世の光である」と言われました。主が付けてくださった塩味によって、私たちの為すことは主のお力によることを示す者であると言われました。真の光なる主からいただいた光で輝く灯として、人々の前に主の光を輝かせ、天におられる父なる神を示すものであると言われました。旅立つ主人から財産を託された僕は、主人に塩味を付けられた者、主人から光を灯された灯とも言えるでしょう。
主人は財産を異なる額で僕たちに預けます。額の違いは「それぞれの力に応じて」なのだと言われます。主は一人一人をよく見ておられて、それぞれが神さまから賜っている力に応じて賜物を与えられます。私たちはそれぞれの生涯に与えられる賜物が同じではないことを良く知っています。私たち以上に一人一人の違いをよくご存知の主が、それぞれの力に応じて託されます。託されるものを負うことは、誰にとっても過剰なものではありません。「私の軛は負いやすく、その荷は軽い」と主は言われています(マタイ11:30)。しかし1タラントン託された者は、自分に負える重みかどうかよりも、他の人よりも少ない額を託されたことへのこだわりをくすぶらせたのかもしれません。
主人は託した値の違いで、優劣をつけることはありません。清算をする時、5タラントンによって更に5タラントン増やした者と、2タラントンによって更に2タラントン増やした者に対して、違う評価を与えていません。全く同じ言葉で彼らの働きとそれまでの彼らの日々を喜んでいます。1タラントン預けられた人も、その財産を活かそうとしていたならば、主人は喜んだことでしょう。
この清算の場面に、神殿で聴いていた人々は驚いたのではないでしょうか。ユダヤの民に良く知られていた譬え話にも、今日の譬えと似ている話がいくつもあったそうです。王や主人が旅立ちの前に僕たちに所有物を託する話です。それらの話しは、いかに忠実に僕たちが託されたものを保管するかどうかに焦点があるのだそうです。ところが今日の譬え話は人々が想定したようには進みません。地中に穴を掘って隠す方法は、当時、最も入念な、安全な財産の管理方法とみなされていたそうです。人々が知る譬え話ならば、この3番目の人は褒められて当然です。しかしそうではないのです。
預かったものを商売によって倍にすることができた最初と2番目の僕のことを主人は喜び、更に財産を託します。3番目の僕は預かったものを活かそうとはしませんでした。取引にはリスクが伴います。減らす可能性も、全て失ってしまう可能性すらあります。一般の取引のようにリスクを恐れ、失敗することを恐れた3番目の僕は、何もしないことを選びます。主人は宝を活かす力がその人にあることを知っており、信頼し、託しました。しかし僕は主人の思いを受け止めていません。自分に活かす力を見ている主人よりも、自分に信頼して宝を託す主人よりも、自分の中の不安や恐れに従います。自分を地の塩とせず、自分を世の光とせず、まるで主人が灯してくれた光を桝の下に置いてしまう者のように、宝を地中に隠します。帰宅した主人に、「ご覧ください、これがあなたのお金です」と掘り出した財産を示す言葉にも、不穏なものを感じます。直訳すると「ご覧ください、これがあなたの所有するものです」という文です。先の二人は預かった財産と増やした財産を差し出して、「ご覧ください。5タラントンです」「ご覧ください。2タラントンです」とその額を述べて、増やしたものについても説明をしているのに、3番目の僕は額も言わず、元の文では「お金」という言葉もありません。“自分は自分のものでもないものを預かっただけ、さあ、盗まれていないし、減らしてもいないでしょう”、そのような何か苛立ちを含んでいるように感じます。地中に埋めていたのは、「あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所から掻き集める厳しい方だと知っていた」から「恐ろしくなっ」たのだと、不正な手段で利潤をあげる主人の側にその理由があるのだとします。自分の行動の責任はリスクを恐れた自分にではなく主人にあるとするのです。それに対し主人は、この僕の自分についての見方が正しいとも間違っているとも言いません。主イエスを敵視していた指導者たちならば、イエスという者は神でもないのに神の子だと言って人々を惑わしていると、蒔かないところから刈り取り、散らさない所からかき集めようとしているのだと、この僕に同調して主イエスを批判したかもしれません。しかしこの譬え話 に神殿で耳を傾けていた人々、また後の時代の教会は、主イエスがそのような方では無いことを知っています。そして譬え話の主人は、リスクが恐ろしいならば銀行に預けて僅かでも利息を得ることができたはずだと指摘し、僕が自分の恐れを取り繕うために主人を非難していることを明らかにします。
1番目と2番目の僕は、取り引きにリスクがあることを知りながら、主人の宝は活かせば活かすほど豊かになることに信頼し、宝を活かすための働きを主人が喜んでくれることに希望をもって宝を活かしました。主人はこの二人のことを「よくやった」と喜び、「良い忠実な僕」と呼んでいます。「忠実な」と訳された言葉は「信頼される、信任を受ける」という意味の言葉です。主人は更に信頼を寄せ、宝を活かす務めを担う者として更に信任を与えます。そして「主人の祝宴に入りなさい」と言います。直訳すると「あなたの主人の喜びの中に入りなさい」という文です。キリストの再臨を語る十人のおとめの譬えがそうであったように、この譬えも天の喜びを祝いの食卓によって示しているのだと思われます。主から託された恵みを誰かと分かち合うために日々を形づくって来た者を主は喜んでくださいます。人が為してきた業が受けるに値するものを遥かに超える喜びで喜んでくださいます。遠くからではなくご自分の祝いの宴の中へと迎え入れ、共に食卓を囲んでくださるのです。
主人は三番目の僕のことは「悪い臆病な僕」と言います。「臆病な」は「怠惰な」とも訳される言葉です。恐れや不安や主人への反発は、萎縮や頑なさへとつながり、宝は死蔵されてしまいました。この者から宝は取り上げられて外の暗闇に放り出されると譬えは語ります。キリストのご意志を真剣に受け止めることなく、託された宝を地中の闇の中に隠すように、あるいは主から灯された火を升の下に置いて闇の中に留めておくように、主から受けたものを閉ざしてしまう臆病さ、その在り方を惰性で続けてしまう怠慢さは、全てが再臨のキリストのみ前で明らかにされること、自分のその歩みが自分を闇へと追いやっていることに、気づいて欲しいと主は願っておられます。主に信頼し、主から託されている宝に信頼し、主の喜びの中へと続く道を進むことを願っておられます。
キリストから託されている宝とは何でしょう。救いの恵みとも、救いを告げる福音とも言えるでしょう。神さまのみ業は聖霊のお力によって今も地上で推し進められています。キリストの弟子たちであるキリスト者たちの手の業が実りを結んでいないように見える時、為していることが徒労に終わってしまうように思える時があります。神さまの宝は決して虚しくは終わらない、からし種が大きく成長し、鳥たちが憩い宿る所となるように、私たちの日々の細やかな業を神さまが豊かに成長させてくださいます。自分のふがいなさ、無力さ、無能さに信仰の目が塞がれてしまいそうな時は何度でもやって来ます。他者を羨み、妬み、不満をくすぶらせ、何かに責任を押し付けていたい思いは私たちの中から消えません。イザヤが歌う、良い知らせを運ぶ伝令のように、平和を告げ、幸いを告げ、救いを告げる知らせを運ぶ者のように、託されている福音が運ぶ者の足を強めます。主なる神が勝利された、あなたの神は王となった、主がすべての力に勝る王であることが明らかになったと、主なる神の支配を否定する力にも、臆病さ、怠惰な思い、頑なさの中にうずくまっていようとする人を暗闇に追いやる力にも、主は勝利されたという喜びの知らせです。それが全て明らかになる終わりの時を見遣ることが、私たちの今の一歩を強めるのです。